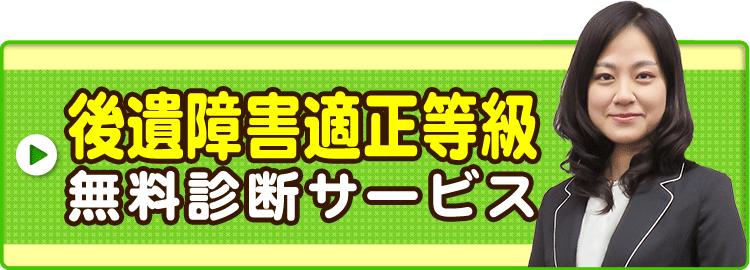高次脳機能障害での症状固定の時期について
1 症状固定って何?
症状固定とは、交通事故で受傷し、ある程度長期間治療を行ってきたにもかかわらず症状が残ってしまった場合で、それ以上治療をしても改善が見込めない状態のことを指します。
症状固定と判断されると、交通事故の治療はその時点で終了となり、加害者は、症状固定時以降の治療費等の支払い義務を免れます。
被害者は、もちろん症状固定時以降も治療を受けることはできるのですが、原則として自己負担での治療となります。
このように、治療費の支払いは加害者側に請求できなくなりますが、症状固定と判断されると、次に述べるとおり、後遺障害の申請をすることが可能となります。
2 後遺障害はいつを基準に判断する?
後遺障害は、症状固定時を基準として判断されます。
そして、症状固定時期が適切なのかは重要です。
あまりに早期に症状固定としてしまうと、後遺障害の有無や後遺障害等級に影響があるかもしれません。
したがって、症状固定の時期は、交通事故被害者の損害賠償上、大きな分岐点となり、非常に重要な問題といえます。
3 高次脳機能障害と症状固定
上記のように、適切な症状固定時期の判断は重要なのですが、高次脳機能障害の場合、その判断は難しいことが多いです。
なぜなら、高次脳機能障害は、身体的機能には特に問題が無く一見しただけでは異常がわかりにくい症状であることが多いためです。
例えば、記憶力の低下、集中力の低下等の認知機能の障害だけではなく、怒りっぽくなる、自己中心的になる、粘着質になる、周囲と衝突しやすくなる等の人格変化も高次脳機能障害の症状の一つであり、これが回復したのか、それ以上治療しても改善困難な段階まで至っているのかは、身体的機能の傷害に比べ見極めが困難であるからです。
したがって、高次脳機能障害の後遺障害の申請は、これらの障害の回復可能性を個別具体的に考えなくてはならないのです。
4 具体的な症状固定までの期間
高次脳機能障害の症状固定時期は、交通事故外傷による脳室拡大等の直接の症状の進行が停止したのかといった点や、片麻痺などの症状もある場合はリハビリ等による症状の回復の程度、他にも学校生活や社会生活、就労への復帰の状況を踏まえ、個別の事案ごとに判断するしかありません。
なお、高次脳機能障害に対するリハビリによる改善効果は、1年ないし2年程度はあるといわれておりますので、1~2年が目安とされることが多いです。
中には、被害者の学校生活や社会生活、就労状況を見極めるために3年以上の長期にわたり治療をして、ようやく症状固定に至ったケースもあります。
高次脳機能障害で弁護士をお探しの方へ むちうちで弁護士をお探しの方へ